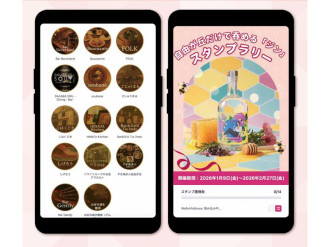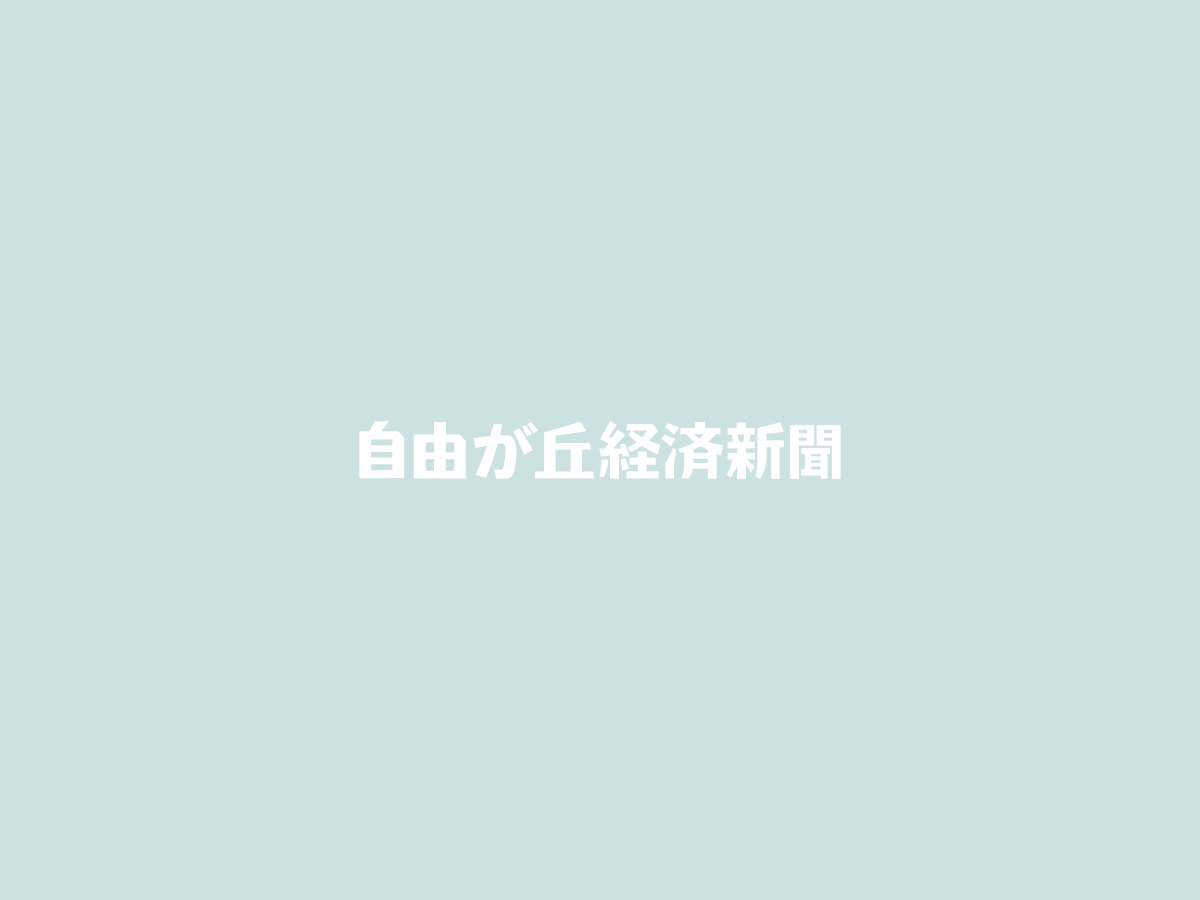自由が丘で「中東カフェ」-ラマダンにおけるイスラム教徒の食生活を紹介

緑が丘文化会館(目黒区緑が丘2)で9月21日、イスラム教徒の宗教行事・ラマダンを通して中東の文化や食を学ぶ「第18回中東カフェ~ラマダンの過ごし方」が行われた。主催は東京外国語大学「中東とアジアをつなぐ新たな地域概念・共生関係の模索」プロジェクト、共催は目黒区国際交流協会(MIFA)。
「中東カフェ」は、報道、援助、ビジネス、文化交流などさまざまな現場で中東と日本をつなぐ仕事に携わるゲストを招き、トークショーや映画などを切り口に中東社会を知るための講座を各地で開催している。
今回は「ラマダン(断食月)」をテーマに、前半は料理教室、後半は講演会形式でイスラム教徒の食文化や生活を知るという趣向。「中東カフェ」事務局スタッフのアレズ・ファクレジャハニさんは「子どもが最初に覚える言葉は『マンマ』が多いそうだが、今回は人間にとって欠かせない『食べる』行為を通して、中東社会の人々がどんな生活をしているのかを知ってもらえたらと企画した」と話す。
料理教室では、中東の家庭料理を提供するチュニジア・レストラン「イリッサ」の女性オーナーシェフ、メリティー・カルソムさんの指導で、ラマダン期間中のイフタール(断食明けの食事)として食べられる軽食・サラダ・スープの3品を作った。
ラマダンは、イスラム暦(太陰暦)によって毎年夏の1か月間が定められ、日の出から日没まで一切の飲食を絶つもの。この日のラマダンは3時45分~17時40分、参加者全員でラマダン明けを待って試食した。メニューの一つ、「包む」という意味の「ブリック」は、茹でたジャガイモにツナやパセリ、香辛料を加えたものと生卵をセモリナ粉の皮(当日は春巻きの皮で代用)に包んでオリーブオイルで揚げたもの。カリカリの皮に半熟状の卵、しっとりとした具がよく合う素朴な味わいだった。
イスラム教徒は豚を一切食べず、手続きによって処理された鶏や牛など「ハラルフード」を食べることで知られているが、チュニジアは地中海に面した土地柄から魚をよく食べるそうで、野菜などの食材や調味料は日本でもなじみのあるものが多かった。異なる点は、材料にアルコールが含まれているものは一切使わないこと。当日使用したサラダのドレッシング用の酢も、中東から取り寄せたノンアルコール酢が使われていた。
講演会では、エジプト出身で東京外国語大アラビア語学科客員准教授のハナーン・ラフィークさんをゲストに、イラクに滞在経験がある「中東カフェ」店長で同大の酒井啓子教授、イラン出身のアレズさんも加わって「ラマダンの過ごし方」についてトークが交わされた。
ラマダンは、病人や家から80キロ以上移動する旅人は免除されるが、子どもから大人まで一切の飲食と悪事が禁止される。「断食が明ける日没30分前は、家路を急ぐ人々で街はラッシュアワー」「断食明けに人に料理を振る舞うとアッラーの神の恵みが得られるとされ、毎日がまるで宴会のようになる」といった現地の様子や、「日本で売られているハラルフードは保存ものが多く、鮮度の面で心配」など日本での苦労も聞かれた。
講演中、同じイスラム教徒でありながらハナーンさんとアレズさんではラマダンの解釈に違いが見られる場面が多々あった。これについて酒井教授は「イスラムは宗派としてだけでなく、国の統治政策として、個人の判断としてなど国によって意味合いが異なり、一つのモデルとなる習慣がないことから議論になることが多い」と説明、中東諸国の多様な生活が垣間見られた。